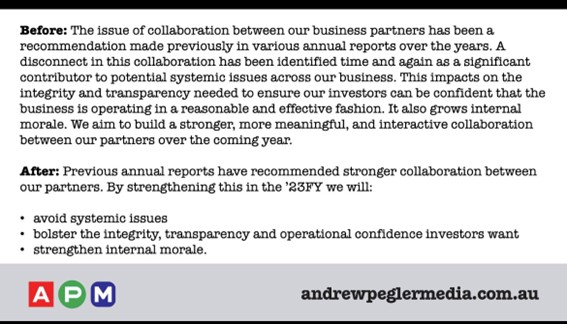グローバル企業が導入するESG時代の新トレンド
企業の情報開示において、マテリアリティが重要であることは広く知られています。近年、ESG時代に合わせてマテリアリティが進化した、ダブル・マテリアリティという考え方が注目を集めています。
ダブル・マテリアリティとは、企業の財務的価値と気候変動など環境への影響、人的資本や社会的問題など、企業と世界全体、両方にとっての重大事項を開示することを促す考え方です。これは、企業が世界に与える影響は金銭的な影響にとどまらないというESG時代の認識に基づいています。
ユニリーバ、ネスレ、ウォルマート、マイクロソフトなどの巨大企業が、ダブル・マテリアリティを統合報告書やCSR報告書に盛り込んでいます。
財務と社会・環境インパクトの2つの要素を分析
ダブル・マテリアリティは、2019年に欧州委員会が「非財務報告に関するガイドライン」で提案したコンセプトです。財務と社会・環境インパクトの2つの観点からマテリアリティを判断することを促すものです。GRI (Global Reporting Initiative)では両方の観点を含めることで初めてマテリアリティとしての意義を持つとしています。
ダブル・マテリアリティの2つの観点とは次のようになります。
- 財務マテリアリティ:投資家に利益を与えるという側面での経済価値創造に関する情報です。企業の発展、業績、地位を理解するため、企業価値に影響を与えるという広い意味もあります。
- インパクト・マテリアリティ(社会・環境的マテリアリティ):投資家、従業員、顧客、サプライヤ、地域社会など複数のステークホルダーに与える経済、環境、人間、社会的な影響などの観点です。
たとえば、ネスレでは、人間や環境と事業の両方へインパクトを与えるマテリアリティとして、原料サプライチェーンによる環境・社会的なインパクトを上げています。
ダブル・マテリアリティをはじめ、企業開示は急激に高度化していますが、これまで以上に開示に至るまでの検討を重ね、その内容がわかりやすく開示されることが非常に重要です。